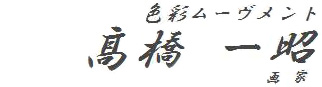―生涯を懸ける課題―
2014年2月4日
2013年の夏は例年になく暑く、気象庁はデータからみて異常気象であると発表した。
そうしたある日、あまり期待しないで入った未知の作家の個展会場で、私はこれまで見たことのない色彩の輝きを持った作品に心を奪われた。 それは連続する色面が立体感をもって、しかも詩情をたたえながら立っていたのであった。 そばまで行きながら見た側面の壁には見事なドローイング作品が数点展示されていたほか、別の壁面には幾何学構成の品性のある作品が目に入った。 私は数人のアーティストによるグループ展かなと判断した。 しかし、そこで出会った初対面の作者は自己紹介した後、これはすべて自分の作品であると述べたのに、私は少なからず驚いた。すぐに退出しようと思って入った画廊であったが、作者と話しこむうち1時間近くが過ぎた。
作家高橋一昭はプロの芸術家であった。 ここでプロという意味は、表現者としてのすべての技術をマスターし、芸術家としての自分を突き放し、時代精神の表現や作品制作の意味を追求し、さらには異文化世界における自分の位置について思考するということである。 こうしたことは、若い柔軟な精神と健康な肉体、充分な外国語使用能力、誠実な人間性や強い目的意識を持ちつつ、トレーニングの場となるべき異国へ単身飛び出さなければ出来ないことである。
話をしながら知ったことであるが、高橋は日本での美術大学入試をやめてフランスへの留学に旅立ったことで、人生の早い時期から異国人としての不自由さや居心地の悪さを体験している。 ヨーロッパでも特にイギリスやフランスなどの先進国は、数世紀前から多くの海外領土を持ち、長期に亘って他民族を労働力として受け入れてきた歴史があるため、外国人に対して特別な配慮をすることはあまりない。 自由競争の多民族国家アメリカでもこの点では同じである。 その土地で学び、稼ぎ、生きていくためには、その土地の言葉を話し、土地の文化を身に付け、土地の人々との信頼関係を獲得しなければならないのは当然である。 高橋は美術教育を受けると同時に、こうしたことを学び取ったに違いない。
彼にとって幸運だったのは、美術大国の入り口で「デッサン」と出会ったことである。日本画の「写生」においてもそうであるが、絵画への道程は先ず眼と腕の鍛錬から始まるといって過言ではない。 美術大学の「デッサン科」専攻で自信をつけた高橋が早い時期にパリで出会ったのが一人の日本画家であった。 高校生時代から関心を持っていた日本画について、画学生高橋はここで基本から学ぶことができたという。 「線と構成」をデッサンから、「濃淡と空間感覚」を日本画から習得した高橋は、乗馬を覚えた少年のように自分の表現確立を目指して走り出した。 そしてこの頃行われた学内展で画商の目にとまったシュール系の絵が、彼のフランス美術界へのデビューとなった。
高橋の作品を見て思い出す言葉がある。 それはかつて美術評論家の故坂崎乙郎が、芸術 とは何かとの問いに対し、『芸術とは詩想を造形化したものである』と回答したことである。芸術の特性を一言で言うのは至難の業であるが、この返答には私も納得するものがあった。高橋作品の魅力の一つは、フランス人画商をも魅了した現実と非現実の対比である。
同一空間に展開された不思議な状況は、現実の風景ともう一つの意識下の風景の並列で ある。 それは時間を超え、空間を超え、論理を超えた姿であり、絵画空間でのみ実現可能な 試みである。かつてマグリットは天上に昼を創り、地上に夜を創ったが、高橋はビルの右側に 昼を、そして左側に夜を描いた。また長い並木の列の一方から新緑の春が始まり、次第に季 節が移って、やがて並木は雪をかぶった冬景色で終わっている。 絵画は視覚芸術であり、 画家はさまざまな冒険や実験を画面上で行うことが許されている。 具象絵画の歴史の長い欧米では殆どすべての制作行為がし尽くされた感があるが、まだ 残された分野があるとすればそれは「イリュージョン」の世界ではないかと思われる。 20 世紀美術のモダニズムはこうした幻想的表現を一切排除してきたが、高橋は頑固に自分 の姿勢を変えようとはしなかった。
高橋のもう一つの魅力として、幾何学抽象の色彩画が挙げられるが、これらは構成と色 彩による産物ではなく、カンデンスキーがかつてそうであったように、風景画の展開から 生み出された必然性のある造形表現である。その動機を知らないものでも、これらの作品 を前にすると柔らかい色調の向こうに何か見えてくるような不思議なオーラを体験する。 鑑賞者が通常抽象画を見る際に感じるある種の緊張感や謎解き意識を全く持つことなく 画面に入り込むことができる秘密は、これが自然界の描写だったからである。
芸術家とは孤独な職業である。デザイナーや建築家と違い、相談したり、協力を求めたりする相手のいない単独作業であり、自分で結論を出す仕事である。半分自信を持ちつつ、半分不安を抱えながら発表の場に臨むのが常である。 高い評価を得たときの高揚感とそうでなかった時の落ち込みの双方を体験しながら作家は育っていくのである。 高橋が孤独な戦いを続ける中で、目をつけたのが見えないものを造形化するというアートの基本線だったのではないか。 キリスト者である彼が旧約聖書の詩篇のダビデの詩と出会って、その詩情に刺激されて制作を開始したことは無意味ではなかった。これまで欧米社会では聖書から数多くの文学、音楽、美術等の作品が生まれているが、今回高橋が発表したような抽象絵画での表現は極めて珍しい。 3千年前のイスラエルの荒地で、天上の神に向って謳ったダビデ王の信仰告白には、率直で表現的な内容に満ちていたに違いない。 美術が誕生したギリシア、ローマ時代に遡るまでもなく、アートの起源は神への賛歌であり、惧れの表現であった。 詩、歌曲、舞踊、演劇、美術、スポーツ、文学はすべて超越者の存在なしには生まれなかった。 西欧社会では宗教を論じる前に、このような文化環境の中での人の営みが続いてきたことから、民族や言語の違いはあるにせよ誰もが自己のうちに「自分の神」を持つに至ったことは自然の成り行きだったに違いない。
フランスにいては日本人であることを自覚し、日本にいてはそこに自分にとっての居場所がないと感じる高橋が、35年の外国生活を通して体感したことは、すべての創作行為の源泉は精神の奥深いところから出てくる民族的な感覚ではないかということではなかったか。 芸術とは何か、自分とは何か、表現とは何か、といった命題は人生を賭けるに相応しいテーマであるが、職業画家の道半ばに達した高橋にとっても残りの人生を懸けて追求するに相応しいテーマではないかと思われる。
美術評論家 金澤 毅